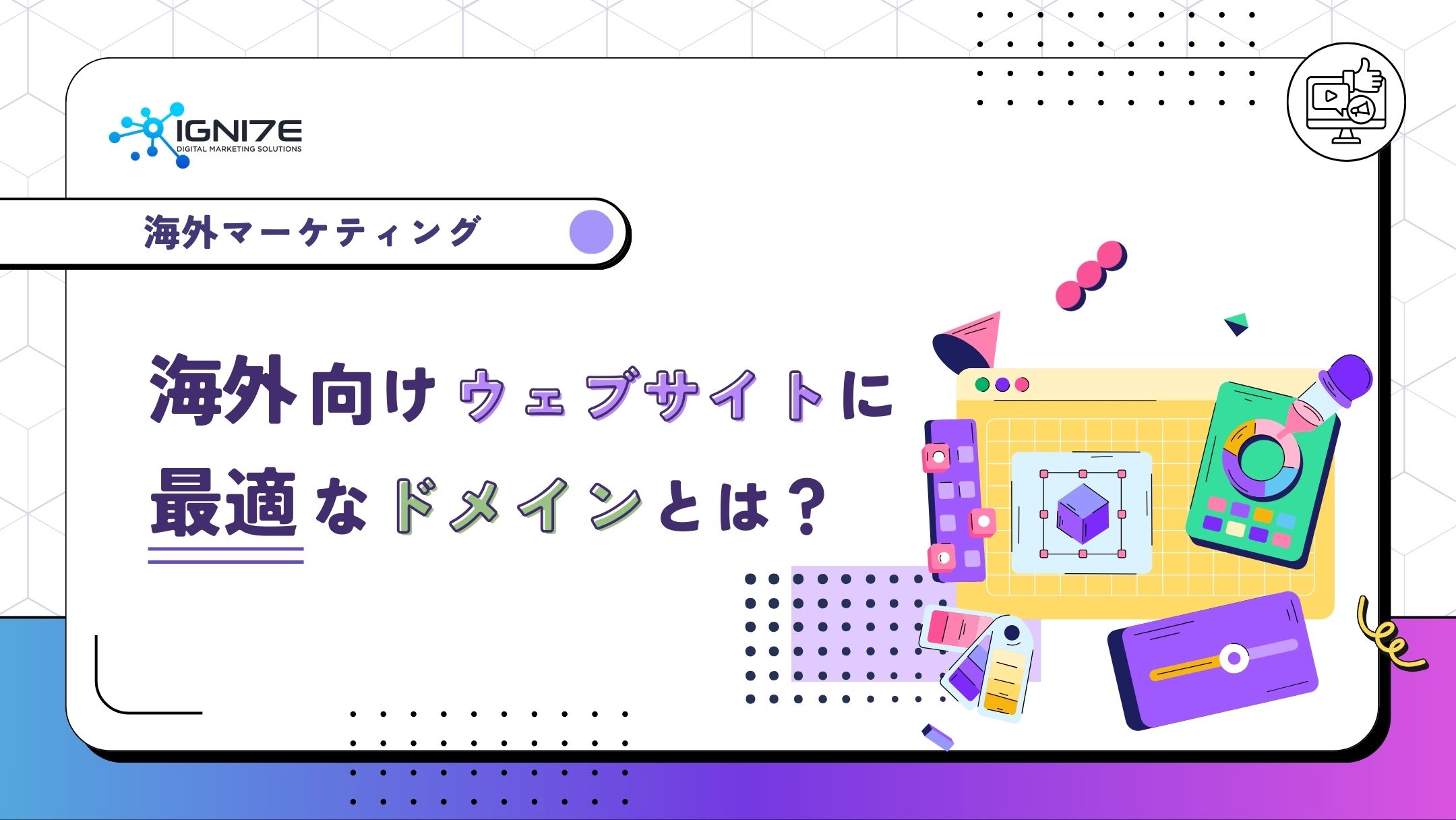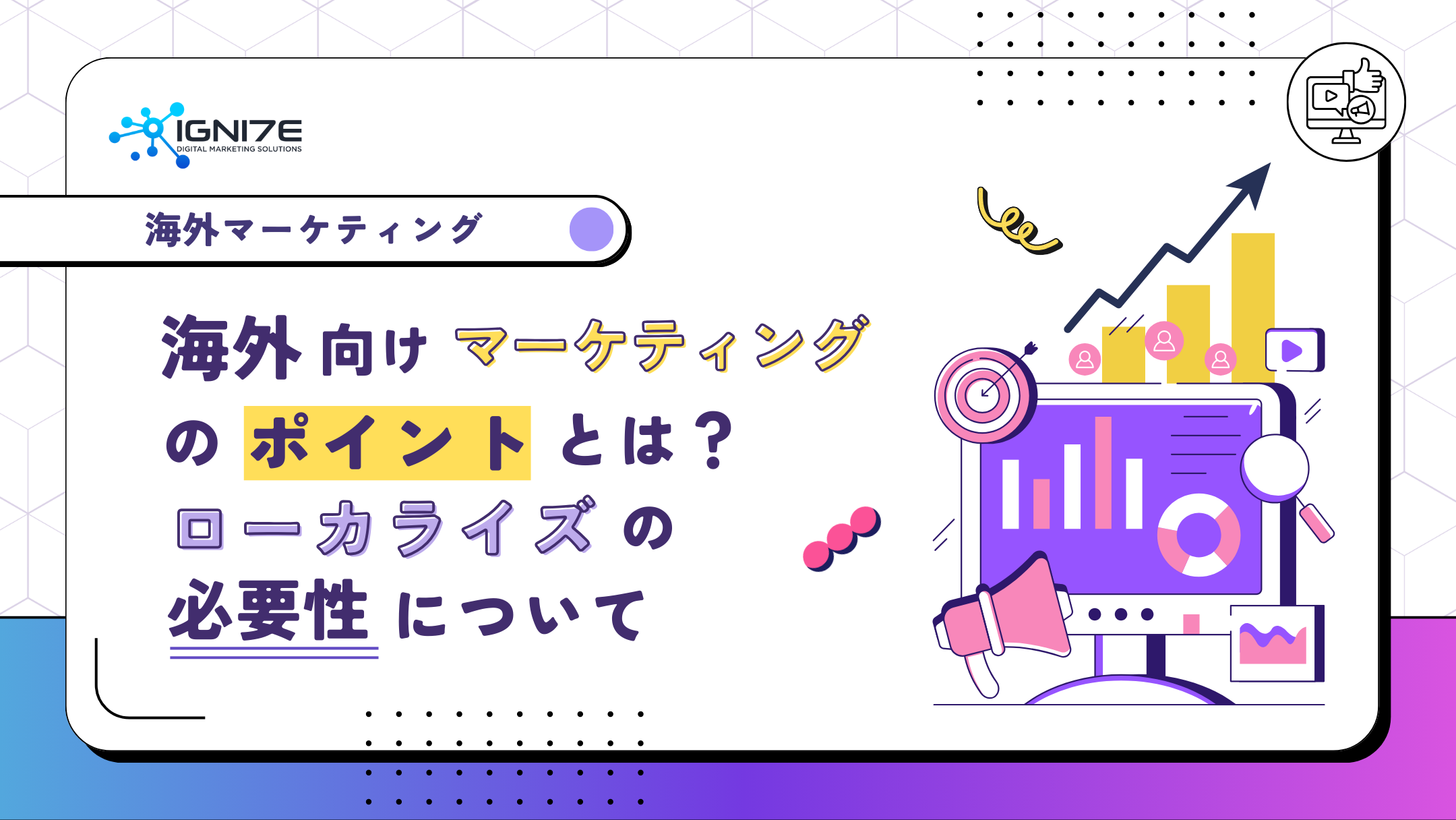政府が観光立国を宣言してからおよそ20年。日本のインバウンド業界は大きく成長し、訪日外国人に向けたサービス展開はビジネスと切っても切り離せない関係となりました。2015年には「インバウンド」という言葉が流行語大賞にもノミネートされました。中でも特に都市部では観光客だけでなく、海外から日本に移り住んで働く方も増えています。
新型コロナウイルスの影響で一時停滞したインバウンド需要も、現在は回復が進み、訪日客数は増加傾向にあります。大阪・関西万博の開催を契機に、国内の受け入れ体制も強化され、今後もインバウンド市場の拡大が期待されています。
▼インバウンド市場規模について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
数あるインバウンドビジネスの中でもとりわけ大きな役割を果たしているのが飲食業界です。ご当地グルメをはじめ、その土地ならではの食べ物を楽しむのは旅行の醍醐味ですよね。中でも世界無形文化遺産としても登録されている日本食は、世界各国で愛される人気料理。それを目的に日本を訪れる方も少なくありません。
飲食業界と言えども、ローカライズされた質の高い翻訳・多言語化を取り入れることはグローバルな活躍を視野に入れるなら無視することのできない重要なポイントです。
今回のブログ記事では飲食店メニューのローカライズ翻訳を行う際に翻訳者が気を付けるべきポイント、そしてその中で得られる学びを「英語翻訳」に特化して紹介していきます。
- 外国人の客層が多く、英語メニューを作りたい飲食店
- インバウンド客を増やしたい飲食店
- よりグローバルにビジネスを展開したい飲食店
- 飲食店クライアントの多い翻訳者
- ユーザにとって使いやすいメニューを作りたい翻訳者
など、上記に当てはまる皆様の参考になれば幸いです。
文化を反映した「ローカライズ」された飲食店メニュー翻訳
近年インバウンドビジネス界で頻繁に目にするようになった「ローカライズ」という言葉。この言葉は翻訳とは切っても切り離せない深い関係にあります。ローカライズ翻訳とはただ言語Aを言語Bに翻訳するのではなく双方の文化や習慣が反映された翻訳のことです。
日本語と英語、日本語と中国語など翻訳を行う際には言語だけでなく双方の文化に対する深い理解が必要です。翻訳者がバイリンガルであることはもちろん大前提ですが、ただ2つの言語を操れるだけでは十分とは言えません。多文化的環境での生活経験があったり、言語の背景にある文化や習慣についても理解することが求められます。
食べ物というのはその土地の文化と密接な関係にあるため、特に飲食店メニューの翻訳ではローカライズが非常に重要になってきます。例えば日本食では直訳するだけでは理解の難しい独自の食材や調理法も多く存在します。
事例 「他人丼」
例えば「他人丼」というメニューはこのような事例の代表と言えます。これは卵と鶏肉の入った「親子丼」に馴染みのある私たちだからこそ理解できる言葉ですが、単純に「他人 → Stranger」「丼 → Rice Bowl」という二つの単語をそのまま訳してしまうと文章を読んでいるユーザーの頭に疑問符が浮かび、一度そこでつまづいてしまいます。
「親子丼」「他人丼」などの商品名は日本の文化と深く結びついているため、日本文化に馴染みのないユーザーの場合、商品名を見ただけで料理をイメージすることはできません。ですのでこの場合はユーザー目線に立って考えると「食材名」を表記して、どのような料理なのかを伝えることが最適な翻訳となります。
(例)
「他人丼」→ × Stranger Rice Bowl ◯ Beef (Pork) and Egg Rice Bowl
事例 「フライドポテト」
また中には日本では当たり前のように使われているものの英語圏では全く通用しない「和製英語」も多く存在します。
例えば「フライドポテト」は日本ではすっかりお馴染みの料理名ですが、英語ではこの名称は使われていません。「Fried Potatoes」と訳すと単に「フライパンで炒めたジャガイモ」というイメージを持たれてしまいます。決定的な間違いではありませんが、ユーザーの混乱を招く可能性があるためこのような表現は避けた方がいいでしょう。
ちなみにフライドポテトはアメリカでは「French Fries」、イギリス・オーストラリア・ニュージーランドなどでは「Chips」という名称で親しまれているため、ターゲットに合わせて翻訳を使い分けるといいでしょう。
(例)
「フライドポテト」→ × Fried Potatoes ◯ French Fries/Chips
料理の注文は読書ではありません。メニューを読むことに時間を費やさずに済むよう、文字をパッと見たときに瞬時に理解ができるような表現を心がけています。
近年はAIを使った翻訳ツールなども発展しつつありますが、このようなローカライズ翻訳は人間だからこそできるものだと言われています。進出先として魅力的な英語圏の市場に対する知識を踏まえた対応は、AIだけでは補いきれません。
翻訳やローカライズについてより詳しく知りたい方は、パンフレット翻訳における注意点やWebサイトの翻訳の仕方、Webサイト翻訳サービスを選ぶ方法などを解説した記事もあわせて参考にしてみてください。
多様な文化的背景に配慮した飲食店メニューの翻訳
次に気をつけなければいけないのがユーザーの多様性に対する考慮です。
日本でも宗教や食生活が多様になりつつありますが、海外のユーザーを想定している場合は日本にない文化的背景を持つ人も多いため、より念入りに配慮する必要があります。宗教によって食べられないものがあるのはもちろん、ベジタリアン、ヴィーガンなどの食生活を送る人も増えています。
もし翻訳ミスにより、ユーザーに宗教的に食べられないものを食べさせてしまったら。命に別条はないかも知れませんが、翻訳者側のミスにより彼らの信仰心を傷つけてしまうこととなります。宗教や主義はアイデンティティの核となる非常に大切なものですので、ここには細心の注意を払って翻訳することが求められます。
多様な文化的背景に対する知識・理解を持つだけでなく、自分の作った英語翻訳が「その先に及ぼし得る結果を想像する力」が大切だと考えています。
宗教や思想などで食べることのできない食材の例
- イスラム教:豚肉、酒など
- ユダヤ教:豚肉、馬肉、タコ、イカなど
- ヒンドゥー教:牛肉、豚肉など
- 仏教:ニラ、ニンニク、らっきょうなど
- ラクト・ベジタリアン:肉、卵、魚など
- ヴィーガン:肉、魚、乳製品、はちみつなど
事例 「ヴィーガン」などの表記をつける
この場合は「ハラル(イスラム教で認められている食べ物を指す言葉)」「ヴィーガン」などの表記やタグをつけることによって、より見やすく検索性の高いメニューにすることができます。
(例)
[Vegan] Falafel Sandwich
飲食店メニューの目的とは何かを考える
3つ目のポイントは「メニューの目的を考える」です。
翻訳者が行う仕事は「翻訳」という言語の変換作業ですが、その根本にある「メニューとは一体何のためにあるのか」を考えなければいけません。メニューの最終ゴールとはもちろん「その料理を選び注文してもらう」こと。そのためにはユーザーに「美味しそう」と思わせる翻訳が大切になってきます。
もちろん翻訳の目的は原文の意味を伝えることですが、翻訳者は飲食店側の目線にも立ち、ユーザーに選んでもらえるような翻訳の一歩先を行く表現を心がけることが大切です。
事例「おいしい」の表現
日本語の「おいしい」という表現は非常に汎用性の高い便利な言葉ですよね。「delicious」「tasty」といった単語を使うのももちろん間違いではありませんが、英語では他にも様々な言葉を使って「おいしい」の表現をすることができます。
savory: 味の良い、塩味のある
appetizing: 食欲をそそる
mouthwatering: よだれの出そうな
flavorful: 風味豊かな
上記のような形容詞を使えば、より効果的に五感に訴えかけるような表現をすることができます。どうせ英語翻訳をするなら、その食べ物の美味しさを最大限に伝えられるような言葉を選びたいですよね。そういった意味で飲食店メニューの英語翻訳は「翻訳+ローカライズ+コピーライティング」の3つの要素が合わさった仕事だと言うことができます。
メニューの見やすさ:媒体によって翻訳の仕方を変える
次のポイントは「見やすさ」です。一口にメニューの英語翻訳といっても見開きの紙メニュー、Webページ、アプリなど様々な媒体が存在します。より見やすいメニューを作るにはそれぞれの媒体の特性を理解し生かすことが求められます。
例えば現代ではスマートフォンの普及によりアプリを英語に翻訳する仕事も増えています。アプリの場合はスマートフォンを使って見ることが前提ですので、スマートフォンの小さい画面では一度に目に入る情報が限られている、ということを念頭に置く必要があります。小さな画面に多くの情報が錯綜しているとアプリとして非常に見づらいものになり、読むのにストレスを感じてしまいます。これは結果としてユーザーが離れる原因になってしまうので気をつけたいところです。
事例 「プラス50円でご飯を大盛りにできます」
例えば日本の飲食店では「プラス◯◯円で味噌汁を豚汁に変更」「プラス〇〇円でご飯を大盛りに変更」などのサービスをよく目にしますよね。
この「プラス50円でご飯を大盛りに変更できます」という文章をそのまま翻訳すると、
「You can upgrade the rice to a large portion for an additional ¥50.」
と訳すことができますが、スマートフォンの画面でこれを見ると数行に渡る長い文章になってしまいます。文章としては合っているのですが画面構成的に少し見づらいですよね。
この場合はシンプルに、
「+¥50 for large portion rice 」
などと要点だけを抑えた言い方をすることで簡潔に伝えることができます。
また、アプリの場合は料理の写真がなく料理名と説明だけが表示されるというケースも多いです。紙のメニューだと全ての料理に写真が付いていることもあり、写真を見ればどんな料理か一目瞭然ですよね。しかしアプリではなかなかそのようには行かないので、ユーザーに料理のイメージを伝える役割は文章が担うことになります。画像のサポートを受けられない分、より表現力の高い文章を書く必要があります。
これらはアプリならではの紙メニューとは異なるポイントですが、このように媒体の特性を汲み取り翻訳の仕方を変えていくことも重要です。こうした「見やすさ」への配慮は、ウェブサイトやアプリのLP(ランディングページ)のデザインやレイアウトにおいても欠かせません。
一貫性のある飲食店メニューの翻訳
そして最後にご紹介するポイントは「一貫性」です。
ここで言う一貫性とは、同じメニューに対して常に同じ英語翻訳を使うと言うことです。
例えば「弁当」は飲食店メニューの中に頻繁に登場する商品名です。「弁当」を英語翻訳する際には「Bento Box」「Bento」「Lunch Box」「Rice Box」など様々な表現方法があります。翻訳者または飲食店の方向性に合わせてどれを使っても構わないのですが、英語訳が統一されていないとユーザーの混乱を招いてしまいます。
事例 「弁当」の英語翻訳
例えば下記のように、同じメニュー上に2つの英語翻訳が混在していたとします。
サーロインステーキ弁当: Sirloin Steak Bento Box
からあげ弁当: Karaage Chicken Bento
日本語ネイティブから見れば「Bento Box」も「Bento」も同じものを指しているということは簡単に分かりますよね。でも、これを全く知識のない外国料理のメニューを読んでいると想像してみてください。2つの言葉は確かに似ているけど、違う料理のことを指しているのかも知れない…と混乱しませんか?
このような混乱を生まないためには、自分の中で「弁当 → Bento Box」などとあらかじめ翻訳を1つに決めて統一することが重要です。
まとめ
以上、飲食店メニューの英語翻訳を行う際に気をつけるポイント5点をご紹介いたしました。
近年は新型コロナウイルスによる落ち込みから回復し、インバウンドビジネスは力強く復調しています。日本企業のグローバル化の進展や訪日需要の高まりを背景に、今後も継続的な成長が期待されています。特に少子高齢化が進み人口が減少しつつある日本では、これからは国内だけでなく海外からの客層にも対応したサービスを展開していくことが成功の鍵となることは間違いありません。
よりグローバルな客層を取り込み成長して行きたいと考えておられる企業、飲食店の皆様はぜひローカライズ翻訳を取り入れることをおすすめします。
各国の文化にローカライズされたより高品質な英語メニューを作成したい方は、過去に20万件以上の店舗へ翻訳を行った実績のある「FlavorJapan」を利用してみませんか?「FlavorJapan」ならお客様のスマホに翻訳したメニューを表示させられるため、よりスマートな対応ができます。気になる方は気軽にお問合せください。
当ブログを運営しているIGNITEは海外マーケティングを中心に、日本の中小企業や個人の海外展開をお手伝いしております。無料診断レポートもありますので、海外マーケティングにご興味がありましたら一度お問合せください。
メールマガジン登録
海外マーケティングに関するノウハウをメルマガで配信いたします



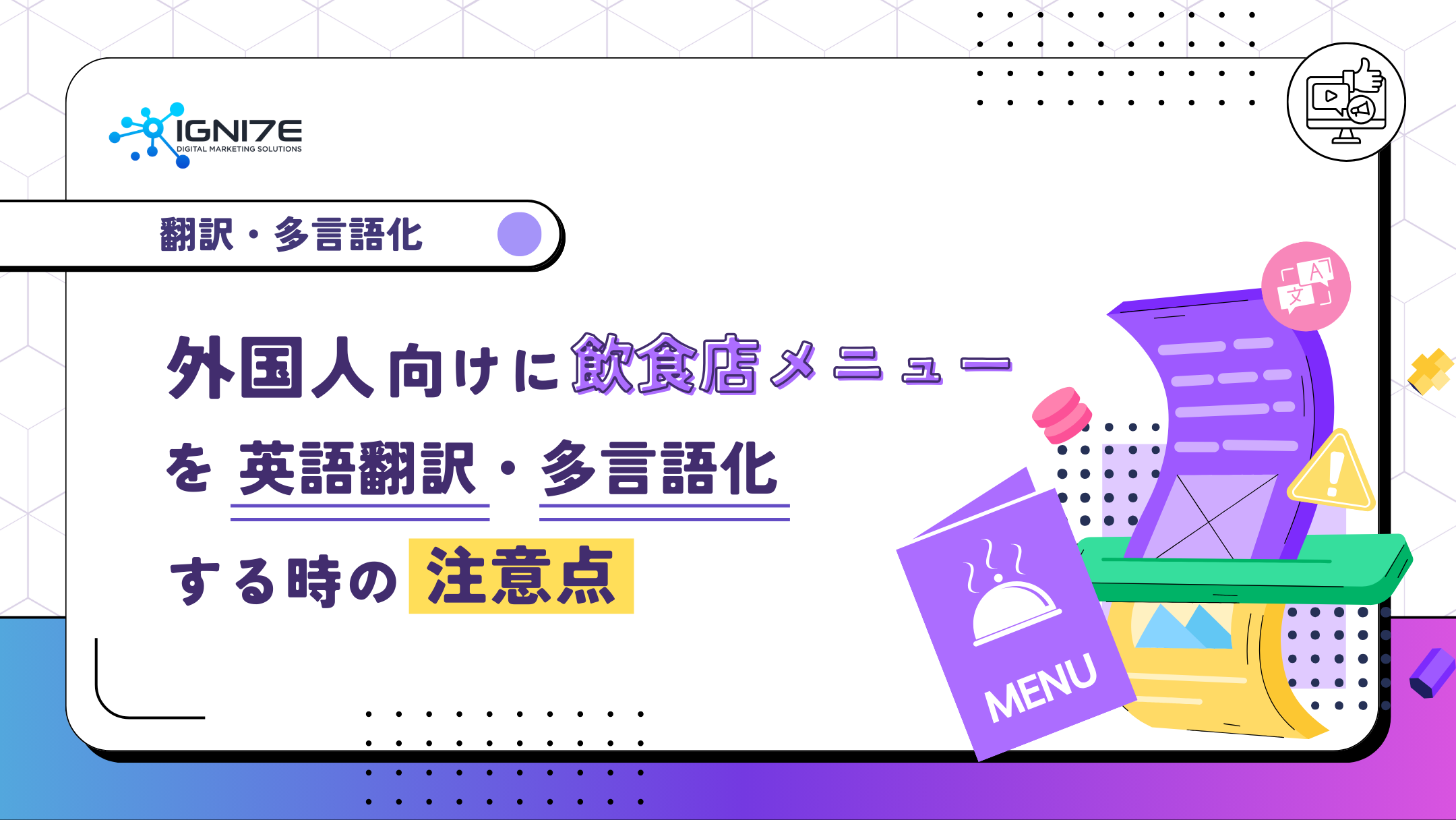



.png)
.png)
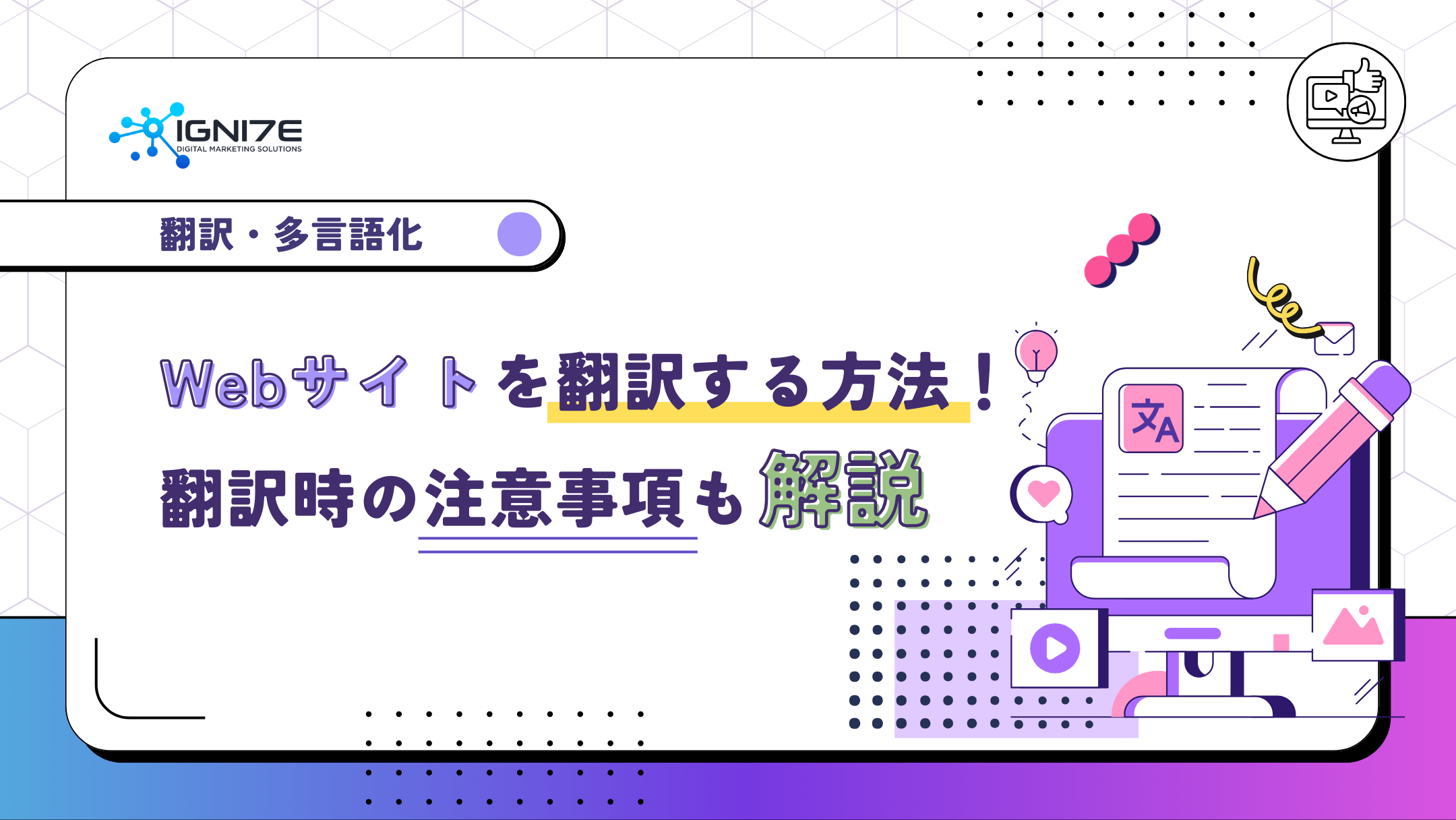
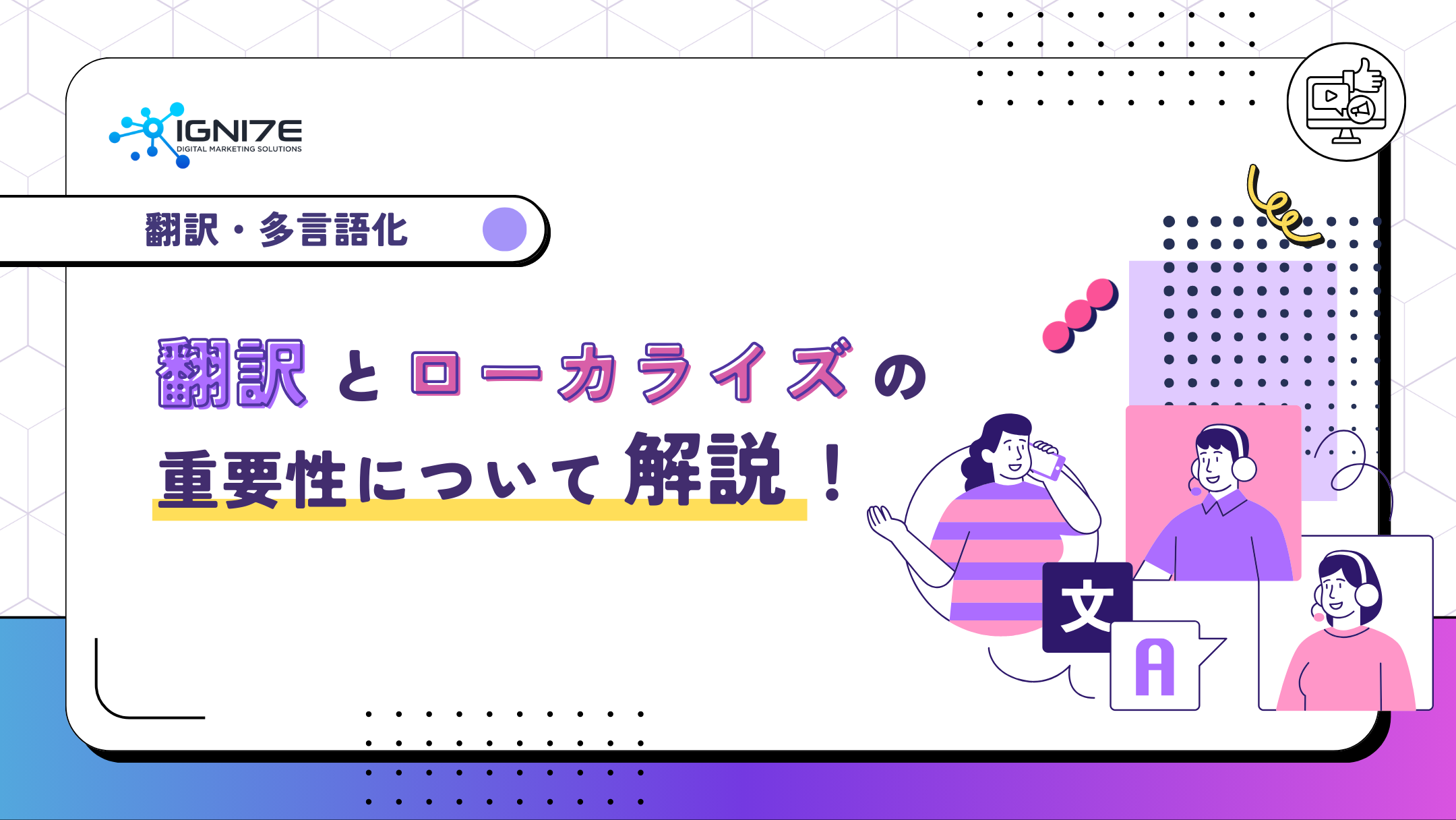
.png)
.png)
.png)