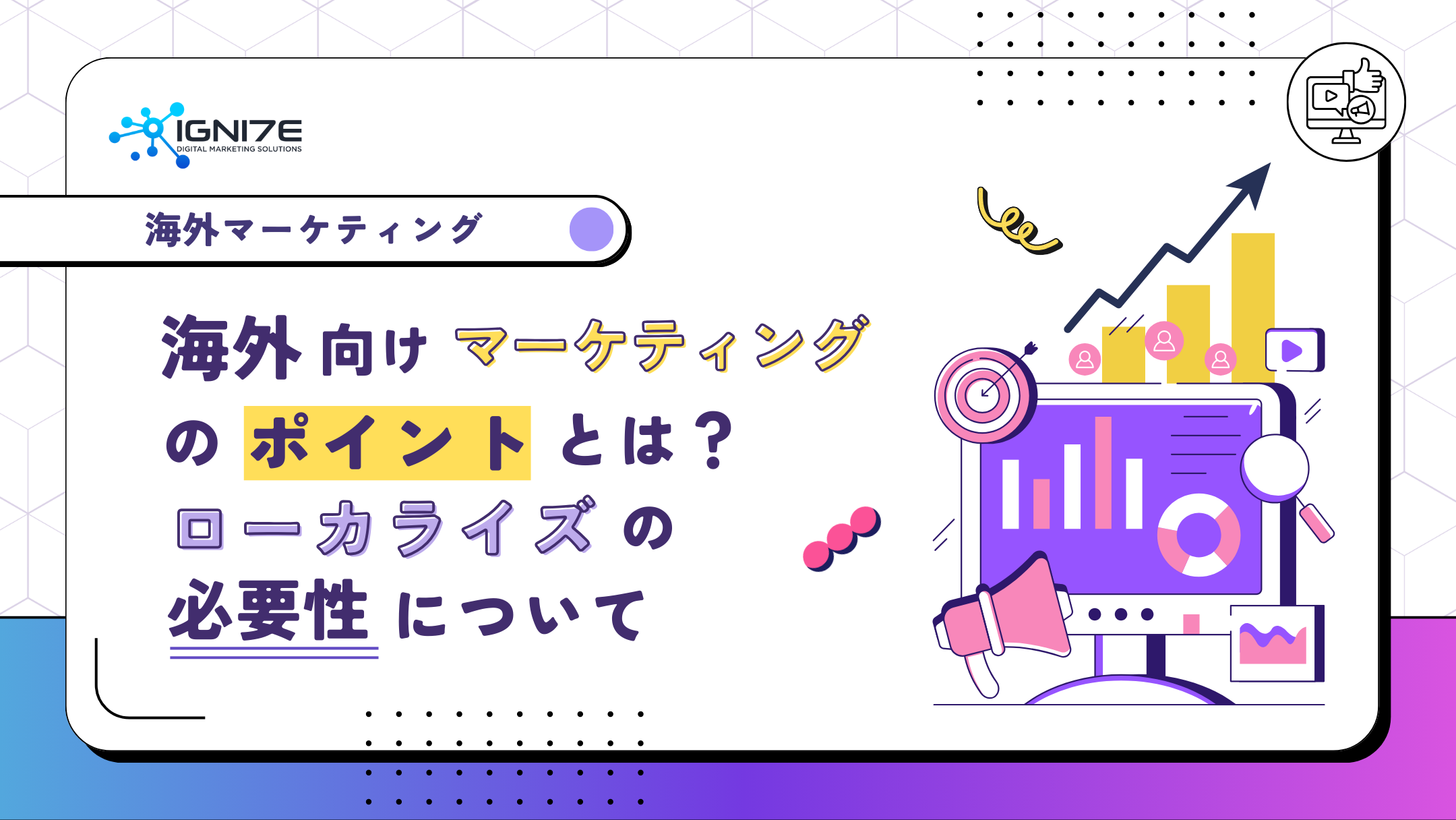多くの企業が戦略を立てながら海外進出を目指す現代では、海外向けのプレゼンテーション資料作成の機会が増えています。
しかし、日本と海外では全く異なる文化を持っているため、単に日本語の資料を翻訳するだけでは十分に伝えることができず、思うような結果が得られない可能性があります。そこで、今回の記事では海外向けプレゼン資料のポイントや翻訳又ローカライズする際に気をつけるべき点について解説します。
海外向けプレゼン資料のポイント
海外向けのプレゼン資料を作成する際には、いくつかの重要なポイントがあります。日本とは異なる文化の理解して最適な戦略を立てること、そして聞き手にとって価値ある情報を明確かつ簡潔に伝えることが重要となります。それでは、具体的にどういったことを意識して作成するべきかご紹介します。
日本と海外の文化の違いを理解しておく
海外と日本のプレゼン資料を比較すると、作成方法や内容に大きな違いがあることがわかります。基本的に日本のプレゼン資料は文字が多く情報量が多いのに対して、海外では図やグラフを使って視覚的に伝えることが主流です。
これらの文化的な違いを理解し、海外の聴衆に合わせたプレゼン資料を作成することが大切です。
【一般的な日本のプレゼン資料】

参考元:社内研修で使用する資料のブラッシュアップをしました - ランサーズ
【一般的な海外のプレゼン資料】

参考元:Architecture Vertical Design PPT Background
伝えたい内容を明確にする
プレゼン資料を作成する際、伝えたい内容を明確にすることがとても重要です。聞き手にとって価値のある情報を提供し、プレゼンの目的を達成するために主要となる伝えたいポイントを絞り込み、論理的に構成する必要があります。具体例や表、データを用いて説得力を高めることで聞き手の理解を促進することも効果的です。
作成の工程を明確にする
プレゼン資料作成は日本向けや海外向けに限らず、作成の工程を明確にすることは重要なポイントです。まず、作成する目的に応じて情報を整理して構成を設計します。翻訳では、AIでの翻訳も活用しつつ、専門用語など適切な英語表現を使用してください。デザインに関しては、ブランドや商品のイメージにも関係するため、統一性のある視覚的に魅力的なスライドデザインを作成しましょう。
そして、必ずフィードバックを収集・修正を行い、最後に全体的な流れや内容の最終チェックをし、必要に応じて修正点を調整します。こうした一連の工程を踏むことで、効果的な海外向けプレゼン資料を作成ができます。
プレゼン資料において相手に伝わりやすい構成とは
プレゼン資料を作成する際、聞き手に伝わりやすい構成を心がけることが重要になりますが、一体どういった構成が良いのでしょうか。このセクションでは、始まりから終わりにかけての流れをわかりやすく解説します。

1. 導入部分・目的
プレゼン資料の導入部分では、結論やプレゼンの目的を先に述べましょう。聞き手がプレゼンの方向性や主旨をすぐに理解することで、聴衆の関心を引き付け、プレゼンの目的を明確に伝えることができます。
また、必要に応じてテーマの背景や問題の重要性を簡潔に説明することで、プレゼンの意義を強調することにも繋がります。
2. 本題
本題では、主要な論点を論理的に整理し、シンプルかつ簡潔に記載しましょう。利き手が資料を見ただけで、ひと目で情報を理解できるように、グラフや図表を活用します。また、説得力を持たせるために、具体例な数字やデータを用いることが効果的です。
3. まとめ・結論
プレゼン資料のまとめや結論では、本題で述べた主要なポイントを再確認し要約します。相手の記憶に残るように最初に述べた結論を再度強調し、必要に応じて今後のステップやアクションプランを示すことで聴衆の行動を促すことができます。
ここでも忘れずに図や写真などを活用して印象に残るような工夫をすると良いでしょう。
プレゼン資料を翻訳する際に注意するべき点

海外向けプレゼン資料を翻訳する際、文化の違いや専門用語の扱いなどのいくつかの重要なポイントに注意が必要です。それでは、海外向けプレゼン資料の翻訳において伝わりやすい表現や適切な用語の選択、レイアウトの最適化、スタイルガイドの活用などいくつかの知っておくべきポイントについてご紹介します。
簡潔で伝わりやすい表現
プレゼン資料の翻訳では、正確さ(Correctness)、簡潔さ(Conciseness)、明瞭さ(Clarity)、の「3C」を意識することが重要です。プレゼンの限られた時間の中で内容を効果的に伝えるために、長文は避け、箇条書きを活用しましょう。日本語をそのままの状態で直訳するとどうしても長文になってしまいがちですが、プレゼンの目的や聞き手のニーズを考慮し、伝えたいメッセージに焦点を当てた表現にすることで海外で通用するプレゼン資料になります。
予算に余裕がある場合は、ネイティブチェックなども検討すると良いでしょう。プレゼン資料の翻訳は、国際的なビジネスコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。正確で伝わりやすい翻訳により、言語や文化の壁を越えて、効果的な情報共有が可能になるのです。
文化の違いへの配慮
海外向けに何かを作成する際には、翻訳だけでなく文化の違いへの配慮するローカライズが必要となります。翻訳だけでなく異なる文化背景を持つ聴衆に対して、海外マーケティングにおいて必要なローカライズを行い、文化的に敏感な表現や内容を避けることが重要です。
国によっては、ハンドサインや牛肉などを使用した画像や例が文化的に不適切であると感じさせてしまうこともあります。誤解や不快感を与えないように各国の慣習や価値観を尊重し、聴衆に合わせた表現を選択することが求められます。
国ごとの専門用語や略語の取扱い
プレゼン資料を翻訳する際、国ごとに異なる専門用語や略語を正確に翻訳することが重要です。各国の業界で使用される用語や略語は、そのまま使用せず、適切な訳語を選択しましょう。また、聴衆にとって理解が難しい場合は、注釈や説明を加えることで、情報の正確な伝達を図ります。
フォントやレイアウトなどの視覚的要素の最適化

レイアウトなどの視覚的要素を聞き手に合わせて最適化することも覚えておきましょう。フォントや文字サイズが適切で読みやすいことを確認し、聴衆が情報を容易に理解できるようにします。例えば、韓国語では「Noto Sans Korean」や「Malgun Gothic」といったフォントがよく使用されますが、英語の国では「Roboto」や「Arial」が主に採用されています。また、言語によって右から左に入力するものや上から下に記載するものもあります。
ローカライズ成功のポイントとなるこうした違いを踏まえた上で、翻訳を行うことも忘れないようにしましょう。
スタイルガイドの活用
プレゼン資料を翻訳する際、一貫性を保つためにスタイルガイドを活用するのも1つの方法です。スタイルガイドに従って、用語や表現の統一を図り全体のバランスを保ちます。これにより、プレゼン資料の質を高め、聞き手に専門的で信頼できる印象を与えることができます。このような相手の信頼性を高めるポイントは、Webサイト制作においても同様です。
また、スタイルガイドを活用することで、翻訳作業の効率化と品質の向上を図ることにも繋がります。リソースが不足する場合などは、必要に応じてWeb翻訳サービスの活用も検討しましょう。
まとめ:グローバルビジネスで成功するための海外向けプレゼン資料作成のコツ
海外向けのプレゼン資料を作成する際、聞き手国の文化の違いを理解し、聞き手に合わせた内容と表現を心がけることが重要となります。伝えたい内容を明確にし、正確で分かりやすい翻訳を行うことで効果的にメッセージを伝えることができます。また、プレゼンテーションの目的として、聞き手のその後の行動を促すことが求められます。そのため簡潔で伝わりやすい表現や専門用語を適切に取り扱うことで、聞き手にプレゼンテーション内容を明確に伝えることができ、効果的なアプローチに繋がります。
こうしたポイント全てを考慮して資料作成をするには、やはり時間と労力がかかってしまうため、プロや専門家に依頼することもおすすめです。効率的にクオリティの高い海外向けプレゼンの資料を作成することは、自社にとって海外進出への重要な第一歩となるでしょう。海外マーケティング成功においては、プレゼン資料の他にもブログなどさまざまなコンテンツの活用が有効です。コンテンツ運用のサポートについてもお気軽にお問い合わせください。
メールマガジン登録
海外マーケティングに関するノウハウをメルマガで配信いたします



.png)


.png)
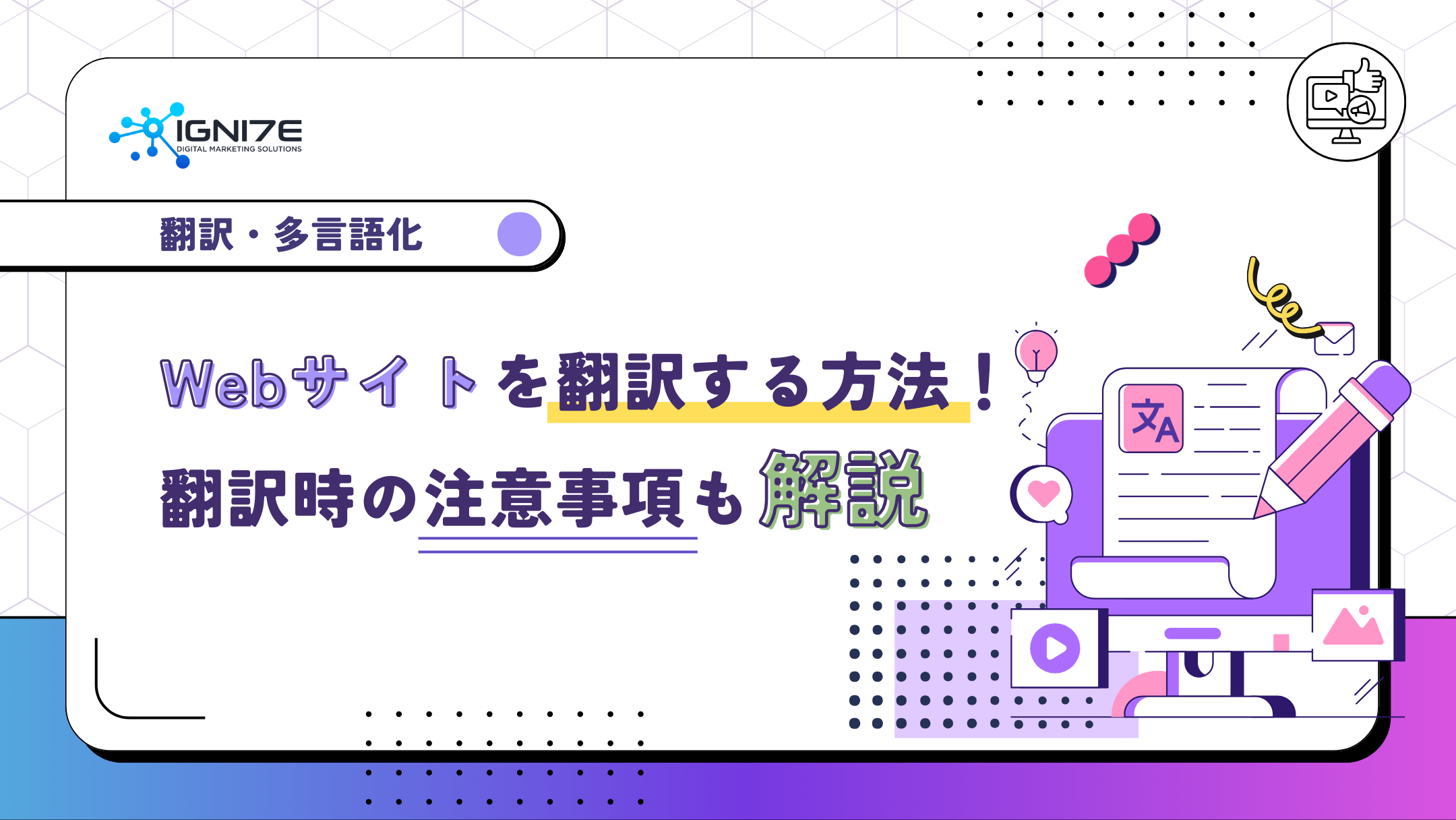
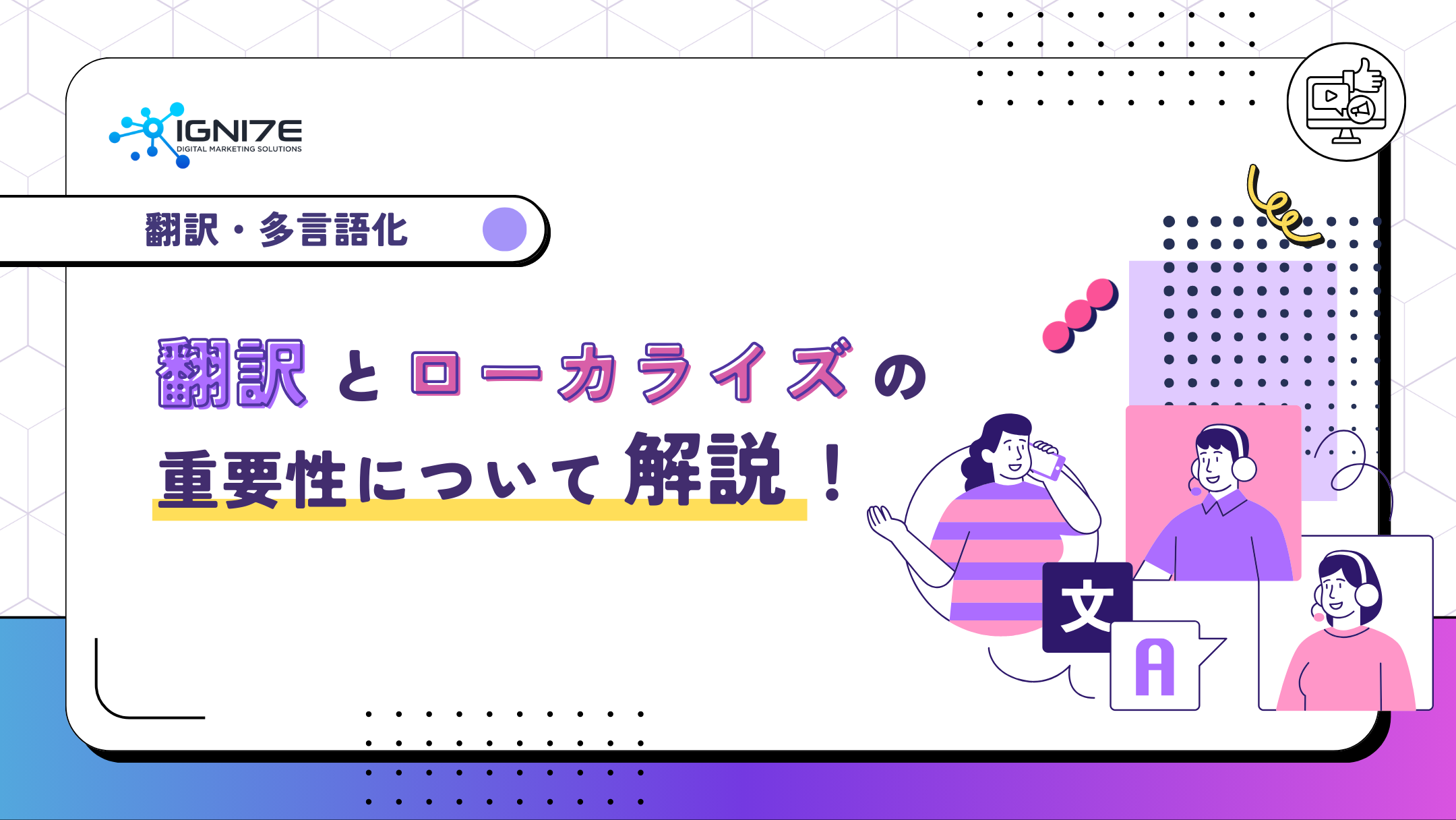
.png)
.png)
.png)
.avif)